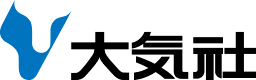Project story 02
大気社の技術を集結させて挑んだ、
これからの農業を支える新事業。
完全人工光型・水耕栽培植物工場
『Vege-Factory(ベジファクトリー)』設立プロジェクト
『Vege-Factory(ベジファクトリー)』設立プロジェクト
地球温暖化による異常気象や後継者不足、フードロスなど、農産物を取り巻く環境は大きく変化している。今後さらにその動きは加速し、世界の農産物の収穫量は伸び悩むとも予測されている。そうした社会課題の解決に向けて、大気社はレタスなどの野菜を生産する植物工場の設立に踏み出した。立ち上げ当初から本プロジェクトを牽引してきた今泉と、最新の設備を誇る杉戸量産実証工場にて生産・開発リーダーを務める大野に話を聞いた。
-
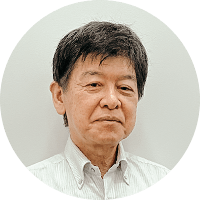 今泉 義光さん
今泉 義光さん
1979年入社
営業部 -
 大野 翔吾さん
大野 翔吾さん
2013年入社
杉戸量産実証工場
生産・開発
挑戦を続けてきた大気社だからこそ、農産という未知の領域に飛び込めた
- 今泉
- このプロジェクトの始まりは2010年に遡ります。空調設備から始まり、塗装システムでも活躍の幅を広げてきた当社は、第三の事業の柱を生み出すために新規事業を育成する部門を立ち上げました。そんな中、食料や農業を取り囲む環境が、異常気象や自然災害、安定供給の難しさなどさまざまな問題を抱えていることに着目したのです。生産量や価格が安定している植物工場産の野菜のニーズは今後ますます高まっていくと予測した上で、これまで培ってきた独自の空調技術やオートメーション技術を活用できないかと考え、植物工場事業への参画を決めました。当時の事業部長が、「今泉、これからは植物工場の時代だよ」と背中を教えてくれたことが今でも記憶に残っていますね。
- 大野
- 私は2016年からこのプロジェクトに参画したのですが、植物工場の事業が軌道に乗るまで、多くの機関と協力しながら進めたと聞いています。自社の研究所や教育機関ともコンソーシアムを組み、工場栽培の技術開発に取り組んだんですよね。
- 今泉
- そうですね。そして2013年に、第一号の植物工場として福井県小浜市の株式会社木田屋商店小浜植物工場グリーンランドを設立しました。プロジェクト立ち上げからおよそ3年。あっという間でしたね。野菜の生産なんて全く未知の領域でしたが、新たな領域に挑戦し続けるという大気社のDNAがあったからこそ、工場設立を実現できたのだと思います。その後は主に北陸や関東地方を中心に、日本各地の植物工場を手がけるようになりました。
- 大野
- 日本だけでなく、海外での工場設立も増えていきましたよね。日本で第一号の植物工場を設立した2年後には、ベトナムの工場も手がけたと聞いています。すぐに海外に広げていけるのは、塗装システムを中心に海外で活躍してきたこれまでの実績があってこそだと思います。

トータルソリューションの提案と地道な販路開拓。その努力が今につながっている。
- 今泉
- ただ、どれほど技術があったとしても、工場の設立を提案するだけでは受注には結びつきません。お客さまからしてみれば、多額を投資して工場を作っても生産物が売れなければ意味がありませんから。そこで、工場の土地探しや補助金の案内、販路の確保支援や長期メンテナンスまで、トータルソリューションを提案するよう心がけました。これまで培ってきた社内外のネットワークを活かした総合的なサポートにより、多くのお客さまのニーズに応えることができましたね。
- 大野
- 社内外のネットワークを活かすと一口に言っても、簡単なことではありません。毎日が地道な活動の連続でした。お付き合いのある一社一社に本プロジェクトについて紹介したり、お客さまの紹介でつなげていただいたり。そうした努力を続けた結果、多くのお客さまに貢献できるようになったのだと思います。自社工場を設立した当初を思い出すと、よくここまで頑張ってきたなあと感慨深くなりますね。
- 今泉
- こうした、本プロジェクトに関わる一人ひとりの努力の結果、今では大手コンビニエンスストアや大手外食チェーンなど、至るところで当社が手がけた植物工場の野菜が使われています。水洗いする必要がないため手間の削減にもつながっているとのことで、植物工場産の野菜の可能性を感じます。

まだまだ伸び代がある。
農産の未来を守るために、新たな技術を生み出して行きたい
- 大野
- 温度と湿度を完全にコントロールできる空調設備や、生育に最適なLEDの活用、多段栽培による土地の有効活用などにより安定供給が可能かつ、劣化が少なく日持ちするためフードロスにも貢献できるなど、当社の植物工場の強みを挙げればキリがありません。
- 今泉
- こうした強みにより、完全人工光型植物工場として、多くの量産型工場の経営を成功に導くことができました。本プロジェクトを通じて、大気社の技術の凄さを改めて感じましたね。
- 大野
- 一方で、まだまだ伸び代があるのも事実です。私たちが手がける葉物野菜は水耕栽培という手法を用いているため、空気と水と光の微細なコントロールが必要不可欠。空気のコントロールは言わずもがな得意なため、これまで光のコントロールに注力してきましたが、次は水のコントロールの技術を磨いていかなくてはと考えています。また、昨今注目されているAIやデータ活用などを導入することで、野菜の成長を予測した先回り対応ができるようにしていきたいと思っています。そしてゆくゆくは、アニメのようにボタンを押したら好きなものがポンと出てくる、そんな自由な社会をつくることが夢なので、葉物野菜だけでなく他の野菜や食品にも挑戦していきたいです。
- 今泉
- 現状に満足せずに、もっと挑戦していきたいですよね。現状、完全人工光型植物工場で栽培された業務用レタスは、全体の出荷量からすると3%にも達していません。つまり、まだまだ参入の余地が大きいということ。まだ植物工場産の野菜の魅力を知らない方も多いと思うので、大野さんが言ったように他の野菜も展開し、国内外を問わず認知度を上げていきたいですね。とは言っても、やみくもに新しいことに手を出すだけではうまくいきません。自分で足を運び、自分の目でその地域や人々のニーズを汲み取った上で、最適なアプローチをすることが大切だと思います。そうしたチャレンジをしてみたい方、未開拓の領域に興味がある方は、ぜひ当社で活躍していただきたいですね。